塾選びで悩んでいる方へ。
この記事は、小3の子どもを通わせていたenaから転塾を決めた私の体験談です。
「塾に通わせてみたけれど、このままでいいのかな?」
そんな不安を抱えている方に向けて、私が転塾を決めた体験談をまとめました。
塾選びに迷っている方の参考になれば幸いです。
enaに入ったきっかけ
コロポン(長男・小3)の中学受験を見据えて、母親の私(ころっとママ)が最初に選んだ塾は、都立中への合格実績が高く、自宅から歩いて通える近さが魅力のenaでした。
コロポンは、保守的で心配性な性格なので、「まずは塾に慣れること」を目的に入塾しました。
*入塾の経緯については、こちらの記事をご覧ください☺️
▶️ はじめての塾選び。都立中受験対策でenaに決めた理由
▶️ 【2025年度版】ena小学部の月謝・入学金・教材費は?実際にかかる費用をまとめました
enaに通ってみて感じたこと
enaに通い始めた頃の生活リズム
enaに通い始めて、コロポンの生活は次のようになりました。
土曜日:午前 習い事/午後・塾(ena)で授業(月末週はテスト)
日曜日:終日フリー
月曜日:学校+学童(17時過ぎに帰宅)、学校の宿題(〜17:30)+塾の宿題(17:30〜18:30)
火曜日:学校+学童(17時過ぎに帰宅)、学校の宿題(〜17:30)+塾の宿題(17:30〜18:30)
水曜日:学校+習い事(19時頃帰宅)、夕飯後に学校の宿題
木曜日:学校+学童(17時過ぎに帰宅)、学校の宿題(〜17:30)+塾の宿題(17:30〜18:30)
金曜日:学校+学童(17時過ぎに帰宅)、学校の宿題(〜17:30)+塾の宿題(17:30〜18:30)
平日は、基本は17時過ぎに帰宅し、学校の宿題をササっと済ませます(これは簡単。真面目な性格なので言わなくても進んでやってくれる)。
そのあと、塾の宿題タイムを約1時間設けていました。
私も夕飯準備をしないといけないので、18時30分を目安に切り上げるようにしていました。
(この1時間が、のちに転塾を考える火種となっていきました。)
ena(小3)の宿題と家庭学習
ena(小3)の宿題は、だいたい毎週こんな感じ。
国語
・テキスト「パースペクティブ」の問題(読解、ことわざ、慣用句など)
・問題集「漢字トレーニング」を使って、毎週18個の漢字を覚える (毎週、確認テストあり)
国語の宿題は、漢字練習がメインでした。(塾では全く扱わず、完全に家庭学習)
学校でまだ習っていない漢字が多いので、こちらのドリルを別途購入して、毎日計画的に勉強していました。
* 旺文社『小学国語 書き順をトレーニング 漢字の正しい書き方ドリル 3年』
➡ Amazonで見る
書き順を確認しながら漢字を練習できるので、とても役立ちました。
もちろん、その計画を立てるのは親の役目。
ドリルの中から、宿題の範囲の漢字18個を抽出し(多い•••)、付箋を貼って、「今日はこの5個を覚えようね」みたいな感じ。
算数
算数は、塾の授業では基礎問題を中心に扱うため、応用問題は基本的には家庭に丸投げ状態•••。
でも、せっかくお金を出して買ったテキストだし、月末のテストでは、その応用問題からも出題があるわけで、やらないわけにはいきません。(入塾時、「塾の月謝は、テスト代がほとんどを占めます」と校長先生も仰っていました。)
コロポンは、基礎問題は解けたり解けなかったりで、特に、応用問題は「お手上げ」状態だったので、夕方の貴重な1時間を使って、私がコロポンにつきっきりで教えていました。
教えて、解かせて、また間違えて、また解き直し…。やっと正解にたどり着く日々でした。
親の気持ち・子どもの気持ち
そんな日々を数ヶ月繰り返すうちに、私の中で潜在化していた、小さな不満が顕在化していきました。
「ほとんど私が教えてるじゃん!!!」
せっかくお金を出してプロに任せているのだから、教えるのは塾の役割。
徒歩圏内の塾だし、質問しに行けばいいのでは?と思ったけど、近所のenaは人手不足が顕著で、いつ行ってもガラガラ•••。生徒も誰1人自習してない。質問しようにも、質問できるような体制が整っていない感じ。「これでは塾に通う意味が薄いのでは?」と感じるようになりました。
コロポンはコロポンで、約1時間の塾の宿題タイムを疎ましく感じているようでした。
真面目な性格なので、やるはやるのですが、日々の会話の中で、この宿題タイムに対してマイナスの発言をすることが多々あり、つきっきりで教えている私は、それを聞いて悲しくなっていました。
転塾を意識したきっかけ
きっかけ① 直感的な違和感
このような生活が続き、「なんか違う」と、直感的に思うようになりました。自分の内側から溢れる声が、このままではダメだと私に囁くのです。これが、私が「転塾」を意識した最初のきっかけでした。
きっかけ② 合格実績の現実
転塾を意識したときに、まず、初心に返ってみました。
なぜenaを選んだのか。それは、①家から徒歩圏内であったこと、②都立中への合格実績がいいことが主な理由でした。
コロポンは真面目でコツコツ型。enaの授業にも、週末の課題にもまじめに取り組んでくれています。
でも——。
毎月行われるテストの成績は、ちょうど真ん中くらい。しかも、教えてるのはほぼ私。このままこの生活を続けて、成績が上がるとは思えません。
果たして、enaのままで都立中に合格できるのか——。
そこで、今流行りのChatGPTに相談したところ、以下のような現実を目の当たりにしました。
現実① 都立中の合格者のほとんどは、ena内でも上位10〜20%にいる子たち
「enaに通っていれば都立中に受かる」わけではなく、都立合格者のほとんどは、ena内でも上位10〜20%にいる子たちです。
🔍 データで見る:enaにおける合格ゾーン
| 成績帯(ena内順位) | 合格率の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 上位10%以内 | 合格率40〜50%超 | 適性検査得点が安定し、作文も高水準 |
| 上位10〜20% | 合格率20〜30%程度 | 学力+作文でミス少ない層 |
| 上位20〜40% | 合格率10〜15%前後 | 実力はあるが作文・時間配分・当日ミスで落ちやすい |
| 下位40%以下 | 合格率は数%未満 | 模試で基準に届かず、記述練度が未成熟なケースが多い |

enaの平均的な子が受かるわけではなく、しっかり上位層に入る必要があるというのが現実です。
たとえenaに通っていたとしても、「都立一本」の戦略では「全落ち」が全然あり得る世界なのです。
都立中合格者の中で、ena占有率が高い理由の、本質的な読み解き方としては
- 都立中受検を第一志望にする層は、enaを最初に選びやすい
- 私立対応は基本的に薄いため、都立特化の塾としてポジションが確立
- enaに都立志望者が集中している=母集団の母数が大きいため、合格者数も当然多くなる
➡ つまり「enaが優れているから多く受かる」というより、「そもそもenaに都立を受ける子が大量にいるから」という構造です。
現実② 都立中の合格者は、実は私立本命組が多い
実は都立中高一貫校に合格する子の中には「本命は私立」という子も少なくありません。とくに、小石川・両国・武蔵・立川国際などの上位都立校になるほどその傾向が見られます。
理由や背景を、以下に詳しく解説します👇
本命私立組が都立にも合格する理由① 四教科で鍛えられた子は適性検査も強い
- SAPIX・早稲アカ・日能研などで四教科を高いレベルで学んでいる子は、「考える力」「記述力」が強い
- 特に算数の応用力+国語の読解力は、適性検査でも大きな武器になる
➡ 本命は開成・麻布・桐朋・早実でも、2/3の都立試験を“記念受験”として受けた結果、合格するパターンが多い
本命私立組が都立にも合格する理由② 受検日が「空いている」ため、試し受験しやすい
- 私立中入試は2/1・2/2が本番ピーク
- 都立中(例:小石川・武蔵など)は2/3に実施される
- 私立で合格校が取れたあと、「合格済みの安心感」で都立を受ける→合格」の流れが多い
本命私立組が都立にも合格する理由③ 難関私立組は試験慣れしていて本番に強い
- 模試・テストを数多くこなしており、緊張への耐性や試験時間の配分感覚が非常に高い
- 適性検査特有の初見資料・作文にも「とっさの対応力」があり、都立型の対策をしていなくても受かってしまうことも

鍛え上げられた難関私立組を相手に、ena単独で合格を勝ち取るのは相当ハードルが高いかも•••。
現実③ ena生の多くは、私立中へ進学している
都立合格者のほとんどは、ena内でも上位10〜20%にいる子たちです。
ということは、ena生の80〜90%は、公立中 or 私立中に進学している、ということになります。
enaに通っていても、私立中の併願校の確保は絶対に必要ということです。
きっかけ③ 適性検査型私立への違和感
都立本命だとしても、私立中の併願校の確保は絶対に必要ということが分かりました。(公立中への進学を許容できる場合は、この限りではありません。)
では、enaに通いながら私立を併願することは可能なのでしょうか。
ena生が併願しやすい「適性検査型」私立中学校
🟢都立型は「質(思考・記述)」に時間がかかり、
🟠私立型は「量(暗記・演習)」に多くの時間がかかる
という違いがあるため、enaに通いながら私立併願を本気で対策するのは「基本的にはきつい」です。ただし、どの程度「私立併願」に力を入れるかによって話が変わってきます。
✔️私立併願が可能なパターン
- 適性検査型を導入している私立校を併願する(例:文化学園大学杉並中、宝仙理数インター)
→ 都立対策の延長線上で受験可能。ena生もよく受ける。 - 2科受験や基礎問題中心の私立を滑り止めにする
→ 少し過去問をやっておけば対応可能
❌ きついパターン
- 開成・麻布・桐朋など難関私立中との併願
→出題傾向もレベルも大きく異なり、算数の演習量・理社の暗記量が圧倒的に必要 - 私立複数校を視野に入れて、入試傾向がバラバラなとき
→「都立対策+学校別私立対策」で学習負担が倍増し、キャパオーバーしやすい
*トータル学習時間の目安(小6の秋以降)👇
| パターン | 平日学習時間 | 土日学習時間 | トータル負荷感 |
|---|---|---|---|
| ena+都立一本 | 平日2〜3時間 | 土日5〜6時間 | ◎ 適性検査に集中できる |
| ena+適性型私立併願 | 平日2.5〜3.5時間 | 土日6〜7時間 | ◯ 効率的に併願できる |
| ena+四科私立併願 | 平日4時間以上 | 土日8〜10時間以上 | ❌ キャパオーバーしやすい |
都立中が本命なら、ena+適性型私立の併願くらいが“バランスのよい併願スタイル”となります。
以上をまとめると、都立中に合格できるのはena内でも上位10〜20%にいる子たちに限られるため、
現時点で偏差値40〜50程度のコロポンがこのままenaへの通塾すると、適性型の私立中学校(例:文化学園大学杉並中、宝仙理数インター)への進学が濃厚となる
ということになります!!(この現実に気付けたのは大きい!)
「適性検査型」私立中学校の進学実績
では、「適性検査型」私立中学校には、どんな学校があるのでしょう。
以下のように、学校によっては「探究重視」で特色がありますが、進学実績だけで見れば、上位都立中高一貫校(武蔵・小石川など)より下回るケースが多いです。
適性型での受験がしやすいからといって、そのまま進学先として選ぶと「この学費でこの実績…?」となることがあり、後悔する可能性もありそうです。
* 進学実績の例(適性型実施校)👇
| 学校名 | 偏差値帯 | 雰囲気・進学実績の例 |
|---|---|---|
| 宝仙学園 理数インター | 偏差値58〜60 | 理系探究型/MARCH・理科大レベルが中心/進学実績は上昇傾向 |
| 文化学園大学杉並 | 偏差値56前後 | 英語・海外系強め/日東駒専〜MARCH/指定校推薦も多い |
| 和洋九段女子 | 偏差値49〜52 | 女子の都立併願で人気/推薦で安定進学/自由な雰囲気 |
| 東洋大学京北 | 偏差値53〜55 | 東洋大への内部推薦あり/成績上位は外部進学も可能 |
| 実践学園・佼成学園など | 偏差値45〜50台 | 都立併願の定番/校風は穏やか/MARCH未満が主力層 |
知らない学校が多い•••。
進学先として「納得できるか」どうかがポイント
このままenaへの通塾を続けると、適性型の私立中学(例:文化学園大学杉並中、宝仙理数インター)への進学が濃厚となるわけですが、小3〜小6の貴重な時間を費やして勉強して、よく知らない私立中学校に、高い学費を払って6年間通わせることになるのって、どうなんでしょう•••。
もちろん、進学先として納得できるならいいんです。でも、私は、どうぜ勉強するなら、どうせ私立に行くことになるのなら、最初から一般的な私立対策をして、もっとたくさんの学校の中から志望校を選びたい、と思ってしまいました。
転塾を決意
- 都立一本は精神的にも現実的にもリスクが高すぎる
- 都立志望だとしても、併願校(私立中)の確保は絶対に必要
- どうせ勉強するなら、四科型の私立中も選べる学力をつけておいた方が安心
- 私立の難関校も本気で狙うなら、最初から日能研やSAPIXなど、四教科カリキュラムの塾で、併願前提で設計した方が効率的
モヤっとした違和感を契機に思考を整理して、以上のような理論が出来上がりました。
こうなると、もう、enaに通い続ける理由はありません。初めは直感で転塾を意識しましたが、理論的にも、納得のいく結論が出たわけです。
そんな中、受験指導専門家のにしむら先生の、このYouTube動画に出会いました。
👉 【知らないと失敗】学習塾の選び方 失敗しない7つのポイント(にしむら先生YouTube)
https://youtu.be/BcEGmOQbYm8?si=OFA8PL8Bj2ZO1skr
中学受験をする上で、塾選びは本当に大事。背中を押された気分になりました。
こうして、自らの直感を信じ(というより、自らの直感を無視できない性ゆえ)、転塾を決意した私は、人生初の、「中学受験の塾選び」の世界へ足を踏み入れることにしたのです。
まとめ
enaに入塾すると決めた時は、「まずは塾に慣れること」を最大の目的に考えていました。
そういう意味では、コロポンの初めての塾に「ena」を選んだことは、良い選択だったと思います。
徒歩圏内で通塾負担は親子ともに少なく、少人数制だったので(クラスの人数は、なんと学年全体で数名•••。笑)、大人数だと緊張してしまうコロポンでも安心でした。
そして、段々と「違和感を感じる」ようになったのは、親子ともに次のステップへ進むための、自然な流れだったのかもしれません。
「塾に慣れる」という目的は達成できたので、次は、いよいよ受験勉強が本格化する小4春に向けて、腰を据えた塾選びをする段階にきているのだと思います。
世の中には、勉強がしたくても、できない子がいて、
勉強をさせたくても、させられない親がいて——。
そんな中、中学受験ができる、どこの塾に行くか迷うことができる、という環境に今自分が置かれている(置いている)のは、何か意味があるようにも思えます。
これからも、自分の直感をベースに中受への道を歩んでいこうと思います。
次回は、約1ヶ月に及んだ塾選びの過程、そして最終的に「日能研」を選んだ理由について綴ります。
よかったらまた覗きにきてくださいね🌸
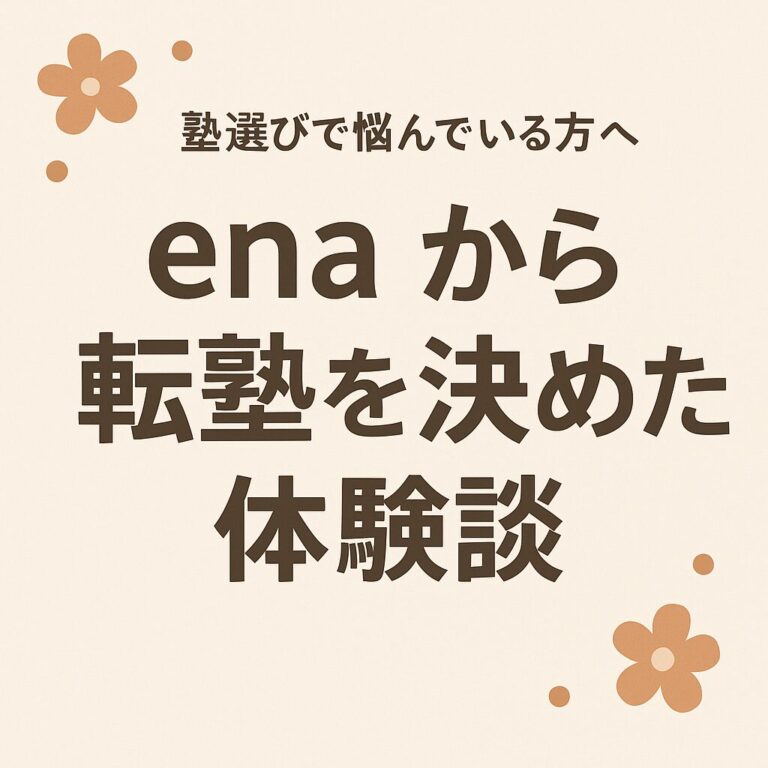
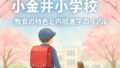

コメント