はじめに
小学校受験を考え始めたとき、「国立・私立・公立ってどう違うの?」という疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
授業内容や進学先、学費まで、それぞれに大きな特徴があります。どの学校が合っているかは、家庭の教育方針やライフスタイルによっても異なります。
この記事では、小学校の種類による違いを、学費・進学・運営の観点からわかりやすく比較します。志望校選びの第一歩として、お役に立てれば幸いです。
【総論】国立・私立・公立小学校の違い
国立小は「教育のモデル校」として、大学と連携しながら先進的な授業や研究が行われます。私立小は独自の理念に基づく個性的な教育方針が魅力。公立は地域密着型で、全国的に標準化されたカリキュラムに沿っています。
| 項目 | 国立小学校 | 私立小学校 | 公立小学校 |
|---|---|---|---|
| 運営主体 | 国立大学法人 (例:東京学芸大学) | 学校法人 (例:慶應、早稲田) | 地方自治体(市区町村) |
| 入学方法 | 抽選・考査あり | 考査あり(難関校も) | 通学区域により決定 |
| 6年間の学費総額 | 約60万〜100万円 | 約600万〜900万円 | 約15万〜25万円 |
| 教育の特色 | 実験的・研究的な教育もあり | 独自の教育理念・施設が豊富 | 標準化された教育カリキュラム |
| 教員の質 | 若手~ベテラン+教育実習生 | 厳選された教員 | 公務員として採用された教員 |
| 中学への内部進学率 | 約20〜80%(内部選抜あり) | 約90〜100%(原則進学できる) | 0%(内部進学制度なし) |
【各論】① 運営主体と教育方針のちがい
国立小学校
✅ 運営主体:国立大学法人
国立小学校は、教育系の国立大学(例:東京学芸大学、筑波大学、お茶の水女子大学など)が運営する附属小学校です。
目的は、①教育実習の場であると同時に、②教育研究を行う「モデル校」としての役割を果たすこと。先生になるための大学生が実習に来たり、大学と連携した最先端の研究授業が行われたりします。
✅ 教育の特色:
- 附属大学の研究校として、探究的・実験的な授業を試行する機会が多い。
- 学費を抑えつつ、質の高い教育が受けられる。
- 教育実習生が関わる場面があるため、授業が多彩・活気あるが、安定性に欠ける面も。
- 学力重視というよりも、「思考力・探究心・協働力」など、学びの姿勢を育てる教育に力を入れている
- 入試を通過した子どもが集まるため、授業のレベルが自然と高くなり、切磋琢磨できる仲間に囲まれる
- 入試を通過しているため、同じ価値観を持つ家庭が集まりやすく、保護者同士のコミュニティや教育意識の高さもプラス
- 中学校への内部進学は「選抜制」で、100%進学できるとは限らないため、適度な緊張感が保てる
私立小学校
✅ 運営主体:学校法人
私立小学校は、独自の教育方針を掲げる学校法人が設置・運営しています。
✅ 教育の特色:
- 教師陣は学校が独自に採用しているため、教員の質が一定
- 少人数・手厚い指導体制。クラスの人数も20〜30人と少なめなことが多い。
- 国や自治体のカリキュラムに縛られない分、先進的な教育内容や独自のプログラム(低学年からの英語教育、プログラミング、国際交流など)を展開
- 担任だけでなく、専科制(音楽・体育・英語など)を導入している学校も多く、専門性の高い授業を展開
- 資金面での余裕がある学校も多く、最新のICT環境・理科室・音楽室・体育館などが充実
- 多くの私立小学校は系列の中学・高校・大学とつながっており、内部進学が可能
- 系列中学を持たない私立小でも、中学受験を前提としたカリキュラムを導入している学校が多数
- 同じ価値観を持つ家庭が集まりやすいため、保護者同士のコミュニティや教育意識の高さもプラス
公立小学校
✅ 運営主体:市区町村などの地方自治体
- 地域の教育委員会が運営を担い、教員は「公務員(教員採用試験を通過)」として配置
- 文部科学省が定めた学習指導要領に沿った標準的なカリキュラムを用いて授業を実施
✅ 教育の特色:
- 学区によって学校の雰囲気は異なるが、基本的には全国一律の教育方針
- 地域住民とのつながりや、地域活動(町内会・防災教育など)と連携した行事が多い
- 教員異動のサイクルが早く、毎年担任が変わることも多い
- 近年は「GIGAスクール構想」などICT教育の強化が進む一方で、自由度は低め
- 多様な子どもたちが集まるため、社会性が育ちやすい
【各論】② 学費のちがい
学校選びをするうえで、6年間にかかる学費は大きなポイントのひとつです。
特に「国立小」は、公立と同じように授業料が無料なうえ、私立に比べて学費がかなり抑えられるのが特徴。
とはいえ、給食費や教材費、行事費などは自己負担があるため、6年間で60万〜100万円前後かかるのが一般的です。
一方で、私立小学校は6年間で600万〜900万円前後が相場。学年が上がるにつれて費用が増えていく傾向があります。
公立小学校は授業料が完全に無償ですが、給食費や学用品代、修学旅行費などが必要で、6年間で15万〜25万円程度の支出になります。
「教育の質」と「費用」のバランスをどう考えるかが、各家庭にとっての選択の鍵になりそうですね。
【各論】③ 内部進学率のちがい
小学校卒業後の進学先も、学校選びでは重要なポイントです。
私立小学校の場合は、ほとんどが系列の中学校・高校を持つ「中高一貫校」であることが多く、内部進学率は90〜100%に達します。外部受験をしない限り、そのままエスカレーター式に進学できるのが大きな魅力です。
一方で国立小学校は、必ずしも全員が系列中学校へ進学できるとは限りません。
選抜試験が課され、合格者のみ(約20〜80%)が附属中学へ進学できます(進学率については学校により差があります)。
公立小学校にはそもそも内部進学制度がありません。

中学受験を避けたい場合は、私立か、内部進学率の高い国立を選ぶ必要があるんだね。
【各論】④ 通学時間・通学手段のちがい
公立小学校は学区制のため、通学は徒歩圏内が基本で、最も負担が少ないのが大きなメリット。
一方で、国立・私立小学校は学区に縛られず広範囲から通える反面、通学時間が長くなりがちです。
特に低学年のうちは、朝のラッシュや乗り換えが負担にならないかも考慮しておきたいところ。
学校によってはスクールバスの有無や、保護者の送迎が必要かどうかも異なるので、事前に確認しておきましょう。
通学時間・通学手段の違いを比較!
| 学校種別 | 通学範囲 | 通学時間の傾向 | 通学手段 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国立小学校 | 広域(都道府県単位) | 30分〜1時間超も | 電車+徒歩が多い | 自力通学が基本。満員電車の負担も考慮必要 |
| 私立小学校 | 全国(都内〜郊外) | 30分〜1時間程度 | 電車+徒歩、スクールバスありの学校も | 遠方から通う子も多く、保護者送迎が必要なことも |
| 公立小学校 | 学区内 | 徒歩10〜20分以内 | 徒歩が原則 | 通学時間は短く、最も負担が少ない |
【各論】⑤ 放課後の過ごし方のちがい
放課後の環境は、学校によって大きく異なります。
国立や私立は「自由度は高いが、親のサポートが必要」な傾向、公立は「公的支援が整っており、安心して預けられる」仕組みが充実。
共働き家庭にとっては、放課後の預かりや学童の有無は“現実的に通えるかどうか”の大きな判断材料になるため、しっかり確認しておくのがおすすめです。
🎒 放課後の過ごし方の違い(国立・私立・公立)
| 項目 | 国立小学校 | 私立小学校 | 公立小学校 |
|---|---|---|---|
| 学校内での預かり | 原則なし(学童なし) | 学校によって有無あり(導入増加中) | 市区町村運営の学童クラブが利用可能 |
| 放課後の選択肢 | 塾・習い事・外部学童が中心 | 課外活動やスクール主催の習い事もあり | 学童・地域の習い事・外遊びなど |
| 保護者の関与度 | 放課後は原則家庭に委ねられる | 一部送迎や参加を求められる学校もあり | 比較的少なめ |
| 特徴 | 柔軟だが家庭の負担が重くなることも | 充実しているが保護者対応が必要な場面も | 公的支援が充実していて安心感がある |
💡 解説ポイント
✅ 国立小学校
- 基本的に「預かりなし」の学校が多く、放課後の過ごし方は各家庭の判断に委ねられる。
- 共働き家庭では、外部の民間学童や塾との併用が必要になるケースが多い。
- 早帰りの日もあり、送迎対応が必要になることも。
✅ 私立小学校
- 近年は「アフタースクール(民間学童と連携)」を整備する学校も増加中。
- スクール内での課外講座(英語・音楽・プログラミング等)がある学校もある。
- 一方で、保護者の送迎や申し込み管理など、家庭側の調整が必要な場面も多め。
✅ 公立小学校
- 地域の公設学童クラブ(〜18時頃まで)が整備されており、料金も安価。
- 放課後も友だちと外遊びできる環境が整っていることが多く、子どもが地域社会とつながる場にもなっている。
- ただし、学習面のサポートは手薄な場合もあるため、習い事や家庭学習で補う必要あり。
どんな学校がわが家に合っている?選び方のヒント
学校にはそれぞれに魅力があり、「どれが正解」ではなく「どれが自分たちに合っているか」を見極めることが大切です。
以下に、選ぶ際のポイントをいくつか挙げてみました。
✅ 1. 教育方針は家庭の価値観と合っている?
- 競争より協調を大切にしたい?
- 礼儀や伝統を重んじたい?
- 自由な発想や探究心を育てたい?
👉 教育理念に共感できるかどうかは、学校選びの軸になります。
教育方針別|向いている学校の傾向
| 教育の価値観 | 向いている学校タイプ | 解説 |
|---|---|---|
| 競争より協調を大切にしたい | 国立小学校、公立小学校 | 詰め込みや序列を強調せず、「みんなで学ぶ・育つ」姿勢が基本。特に国立は協働・探究型授業が多い。 |
| 礼儀や伝統を重んじたい | 私立小学校(伝統校) | 校訓や礼法・制服などを通して、人格形成や行儀・品格に力を入れている学校が多い(例:早実・暁星・白百合など)。 |
| 自由な発想や探究心を育てたい | 国立小学校、特色ある私立小学校 | 国立は大学と連携した探究型教育が強み。私立にも「自由進度学習」や「PBL(探究)」を導入している学校あり(例:玉川学園、和光小など)。 |
✅ 2. 中学受験をする予定かどうか
- 中学受験を避けたい → 私立一貫校や国立の内部進学も選択肢
- 受験を視野に入れている → 受験対応の私立や国立も候補に
👉 進学までの「見通し」を持っておくと、選びやすくなります。
✅ 3. 家庭の通学・生活リズムと合っているか
- 毎日の通学時間は?体力的に無理がないか?
- 習い事や家族時間とのバランスは取れるか?
- 親の関与度はどれくらい求められる?
👉 特に共働き家庭の場合は、放課後や保護者の出番も要チェック。一般的に私立小学校は、保護者の関与が多く求められる傾向があります。
✅ 4. 家計とのバランスはどうか
- 「投資」としての教育費をどう捉えるか
- 無理のない範囲で、納得して払えるか?
👉 私立は高額だが手厚い、国立はコスパ重視、公立は最も抑えられる。
✅ 5. 子どもにとっての「居場所」になるか
- 学校の雰囲気に合いそう?
- 子どもが「通ってみたい」と思える環境か?
- 見学や説明会での子どもの反応は?
👉 最終的には、子どもがどう感じたかも大切な判断材料です。
💬 まとめ:学校を「選ぶ」のではなく「合う環境を見つける」
学校の選択は、子どもだけでなく家族全体の暮らしにも大きく関わるもの。
とくに共働き家庭では、通学・放課後・保護者の関わり方など、現実的な視点も大切になってきます。
教育の理想と、日々の生活のバランスを取りながら、「無理なく、心地よく通える学校」を見つけられるといいですね。

このブログでは今後、具体的な学校ごとに、教育方針・入試情報・進学実績などを詳しくご紹介していきます。
志望校を検討されている方は、ぜひそちらも参考にしてみてくださいね。


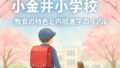
コメント