🔗 【小学校受験編】志望校選びシリーズ
以下の記事もあわせてご覧ください:
- 👉 【東京都立】立川国際中等教育学校附属小学校について
- 👉 【私立】桐朋学園小学校について(執筆中です)
- 👉 【国立】東京学芸大学附属小金井小学校(※本記事です)
小学校受験を考える中で気になった“国立の名門校”
わが家では、ぽわまる(年中)の小学校受験を見据えて、さまざまな学校を調べています。
今回ご紹介するのは、国立の名門「東京学芸大学附属小金井小学校」。
「研究校」としての特色ある教育方針や、附属中学への高い進学率など、調べるほどに魅力が見えてくる学校です。
わたし自身も最初は「なんとなく有名」というイメージだけだったのですが、教育理念や行事、入試内容などを知るうちに、「ここに通わせてみたいかも」と思うようになりました。
今回は、そんな東京学芸大附属小金井小学校について、
- 教育の特色
- 入試の流れと倍率
- 進学先や附属ネットワーク
- 家庭でできる受験対策
などを中心に、保護者目線でわかりやすくまとめてみました。
これから学校選びを始める方の参考になればうれしいです。
※「そもそも国立小学校って、公立や私立と何が違うの?」と感じた方はこちらの記事もどうぞ👇
👉 【徹底比較】国立・私立・公立小学校の違いとは?学費・進学・教育方針をやさしく解説!
東京学芸大学の附属校は4つ!それぞれの特色とは?
東京学芸大学には、附属小学校が4校あります。それぞれの学校には個性と教育方針が異なり、所在地も異なります。以下に整理しました👇
📚 東京学芸大学の附属小学校4校
| 学校名 | 所在地 | 特色 | 募集枠 | 倍率(2024年度) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京学芸大学附属小金井小学校 | 小金井市(JR武蔵小金井駅 徒歩圏) | 教育研究重視。中・高と一貫した教育 | 男女計105名 | 男約9倍・女約10倍 ※実質倍率約3.9倍 | 試験通過後に抽選あり。系列の附属小金井中へ進学。 |
| 東京学芸大学附属大泉小学校 | 練馬区(大泉学園駅) | 探究型・IB教育に注力 | 男女計90名 | 男女とも約15倍 | 第一次抽選あり。附属国際中等教育学校へ内部進学。 |
| 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 世田谷区(上町駅・桜新町駅) | 地域連携と人間教育を重視 | 男女計105名 | 男女とも約11倍 | 安定した人気。附属世田谷中学校へ進学。 |
| 東京学芸大学附属竹早小学校 | 文京区(茗荷谷駅すぐ) | モデル校としての教育実践 | 男女計40名 | 男約59倍・女約58倍 | 圧倒的な高倍率で狭き門。第1次・第3次で抽選あり。附属竹早中へ進学。 |
📌 補足情報
小金井小学校
出願段階では男女とも約9~10倍ですが、出願後の辞退や欠席が多く、実際の試験倍率は約3.9倍。合格者は試験で選び、そこから抽選で最終定員に調整(抽選倍率:男約1.8倍・女約1.7倍) 。
大泉小学校
2024年度は第一次抽選後の試験で15倍前後。IB(国際バカロレア(International Baccalaureateというスイス・ジュネーブ発祥の世界共通の教育プログラム)導入校として人気の高さも倍率に反映 。
世田谷小学校
安定した人気校で、倍率は男女とも約11倍。
竹早小学校
“教育の竹早”と呼ばれるほどの、伝統と実績を誇るモデル校。教育内容・立地・進学ルートすべてにおいて魅力が高く、60倍を超える超高倍率も納得の人気校
東京学芸大学附属小金井小学校の特徴と魅力
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学校名 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |
| 所在地 | 〒184 – 8501東京都小金井市貫井北町4−1−1 JR 中央線 武蔵小金井駅北口より ●京王バス / 6番乗り場中大循環【学芸小前】下車 ●徒歩 / 15〜20分 *中等教育学校と同じ敷地・住所 |
| 設立 | 1911年創立(豊島師範学校附属小学校として) 1959年に小金井で開校し、現在の姿に。 2011年に創立100周年を迎えた、伝統ある附属小学校 |
| 生徒数 | 附属小学校(小1〜小6) 1年から6年まで 24学級、児童数 1,007名 |
| 学区 | 通学区域制限あり 東京都内の通学時間が 40分以内 の地域を一部含む町全体 |
| 制服 | 冬服 女子:ブレザー+ジャンパースカート、丸襟ブラウス 男子:ブレザー+シャツ+ズボン 色は濃紺系 夏服 女子:ワンピース型、または半袖ブラウス+スカート 男子:半袖シャツ+ズボン 特徴 女子のジャンパースカートはチェック柄との情報あり |
| 生徒会 | 生徒会選挙が行われ、立候補者は演説をして全校投票で役員が決まる。 活動内容や役員構成などの詳細は公開情報が少なく不明。 |
| 行事 | 4月:入学式、1年生を迎える会 5月〜7月:遠足(低学年)、宿泊行事(3〜6年)、水泳会 10月:なでしこ運動会 11月:低学年秋祭り 12月:音楽会(3年に1回) 2月:展覧会、研究発表会(いずれも3年に1回) 3月:6年生を送る会、卒業式 |
| 給食 | あり 自校方式(委託調理)。校内の給食室で調理 |
| カリキュラムの特色 | 研究校ならでは:文科省の学習指導要領に沿いながらも、独自の研究テーマを設定して授業を工夫 思考力・表現力を育成:子どもが自分で考え、表現する学びを重視 宿泊行事がカリキュラムの柱:3年生から宿泊学習を経験し、自主性や協調性を身につける ICT活用:全教室に電子黒板を導入し、タブレットなども取り入れた先進的な授業 多様性に配慮:子どもの発達や学びのスタイルに合わせたインクルーシブ教育を実践 |
| 施設 | ・昭和期建築が中心で古さがあるものの、改修や増設により老朽化を抑えている。 ・東京学芸大学の小金井キャンパス内にあり、大学関連施設と近接・連携している。 ・学校専用の宿泊施設を持っており、3年生~6年生の宿泊行事(自然体験・共同生活)で使われている「至楽荘(千葉県勝浦市)」と「一宇荘(長野県)」などがある。 |
| 教育目標 | 明るく思いやりのある子 強くたくましい子 深く考える子 |
| 学費・必要経費 | ・授業料無料(国立小学校のため) ・6年間の学費総額はおおよそ 100万円前後。私立小学校(6年間で600〜900万円かかることが多い)と比べると、かなり経済的といえる。 |
| 進学の流れ | 東京学芸大学附属小金井中学校 へ内部進学できる可能性が高いが、選抜試験はある。 「約8割が内部進学し、残りは私立や地元公立中へ進む」というのが実情 |
内部進学後の進路(附属中・附属高含む)
学芸大附属の「内部進学」は中学までが中心で、高校・大学へのエスカレーター制度はありません。結果的に附属中から附属高へは3〜4割程度、大学へは一般入試で進学するしかなく、“附属”=自動進学ではないのが大きな特徴です。
| 主な進路・割合 | |
|---|---|
| 小→ 中(偏差値59前後) | 選抜試験により、約8割が附属小金井中へ内部進学 |
| 中学→ 高校(偏差値74〜75) | 選抜試験により、約3〜4割が附属高等学校へ進学 |
| 高校 → 大学 | 内部進学制度がないため、大学受験必須。 ただし附属高の生徒は学力レベルが高いため、東大・一橋・早慶など他大学へ進学する生徒も多く、大学進学先は多様 |

中学校から高校への内部進学率がかなり低くてびっくり•••。
学芸大附属小金井小に入るメリット
学芸大附属小に入っても、残念ながら大学までエスカレーター式に進めるわけではありません。多くの子が高校受験、そして大学受験を経験します。
それでも敢えて国立小学校を受験するメリットはどこにあるのでしょうか。以下まとめてみました。
- 学費が安い
授業料は無料で、私立のような高額な学費が不要。6年間でかかる費用は約100万円前後と、公立並みに抑えられる。 - 教育研究校ならではの先進的な授業
教育実習生の授業や研究テーマに沿った授業が展開され、子どもが「考える力・表現する力」を伸ばせる。ICT活用や探究型学習にも積極的。 - 宿泊行事や特色ある学校生活
3年生から宿泊行事があり、自然体験や共同生活を通して自主性・協調性を育てる。運動会や展覧会なども充実。 - 多様な家庭の集まり
都内各地から児童が通い、保護者層も幅広い。一般公立より教育意識の高い家庭が多く、子ども同士もよい刺激を受けられる。 - 中学受験にもつながる力
内部進学で附属中に進む子が多い一方、私立中や難関都立中を受験する子も一定数おり、学校の学習が「中学受験準備」と相性が良い部分もある。 - 「附属ブランド」
「国立附属」という安心感や社会的評価があり、履歴として残るのも強み。

「小学校時代をどう過ごすか」を大事にしたい家庭にとって、国立小学校の教育環境は大きな魅力。“子どもの6年間を豊かにする”という視点で選ばれている学校です。
私立一貫校とは違う“国立附属小”という選択
学芸大附属小金井小学校は、大学までの一貫校ではなく、中学・高校・大学受験を経る必要があります。そのため「せっかく小学校受験をしたのに、また高校受験・大学受験をしなければならない」という現実に驚く方も多いでしょう。
それでも、この学校には「学費を抑えながら質の高い教育を受けられる」「宿泊行事や探究的な学びで子どもの自主性を伸ばせる」「多様な仲間との出会いがある」といった大きな魅力があります。
つまり附属小に入学する意味は、単なる“進学の安心ルート”ではなく、小学校6年間をどんな環境で過ごすかに価値を見出すところにあります。伝統ある校舎で、多様な仲間と共に育つ時間は、子どもにとって一生の財産になるはずです。


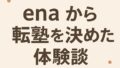
コメント